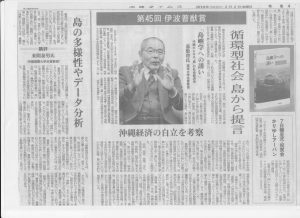「日本島嶼学会研究奨励賞」は、本会の若手会員の顕彰を目的として2014年度に設置されました。2017年度の受賞者は、真崎 翔会員でした。
自薦による応募者の中から若干名の受賞者を選考し、大会において表彰するとともに1万円の賞金が副賞として贈呈されます。
受賞候補者の募集を下記の要領で行いますので、奮ってご応募ください。詳しくは、以下の応募要領をご覧ください。
日本島嶼学会 会長 中俣 均
応募要項(PDF)
—————–
日本島嶼学会研究奨励賞応募要領
日本島嶼学会研究奨励賞(以下奨励賞という)の応募に当たっては,この要領に従って,応募申請書に必要事項を記入し、PDFファイルにして、選考委員長あてメールに添付して提出してください。
応募資格 2018年4月1日現在45歳以下の本学会の会員
応募〆切 2018年6月2日(土) *期間を延長しました。
申請書送付先 研究奨励賞選考委員長 小西潤子 ejkonis@gmail.com
申請書の様式は自由ですが、以下の項目を含んでください。
(1)応募年月日
(2)申請者氏名
(3)生年月日および2018年4月1日現在の年齢
(4)出産・育児・介護・その他の事由のため研究中断がある場合はその期間
(5)学位(取得年月、学位名称、取得大学・研究科名)
(6)現在の専門分野
(7)所属機関・職名(学生の方は2018年4月1日現在の学年)
(8)連絡先住所(所属あての場合は所属機関名も)・メールアドレス
(9)最終学歴
(10)応募研究課題
(11)応募研究の業績の大要(A4用紙1枚以内)
(12)今後の研究の展望(A4用紙1枚以内)
(13)応募研究の内容をもっともよく表していると考える論文・発表要旨等1篇(スキャンしたPDFファイル等で可)
(14)応募研究にかかわる業績リスト
以下の項目に分けて記載すること
1)学会誌「島嶼研究」に発表した論文
2)本学会の大会での発表
3)その他本学会の中での報告、各種活動、作品等
4)本学会以外の学会誌等に発表した論文(著書を含む)
5)本学会以外の学会等での発表、各種活動、作品等
(15)競争的研究費の採択状況(代表者のみ)
(16)他の学会賞等の受賞歴(学会名、受賞名、受賞年、受賞タイトル)
選考の過程で追加資料の提出をお願いする場合があります。
以上
応募にあたっての補足
(1)「応募研究課題」 とは、研究奨励賞に応募いただく研究全体のテーマです(すでに学会等で発表された個別のタイトルではなく)。
(2)「応募研究にかかわる業績リスト」 は、本学会に関係するもの(「島嶼研究」や大会での発表など)だけでなく、応募された研究テーマに関連するものを 記載ください。応募される研究テーマと関係がないものは含めなくてけっこうです。また、既往両3年以内の研究業績を中心に評価します。
(3)「競争的研究費の採択状況」は、応募研究に関するものを記載ください。
2018年度 日本島嶼学会研究奨励賞選考委員会
————————
【参考】
日本島嶼学会研究奨励賞に関する規則
(2013年11月24日制定、2014年9月5日一部改訂、2015年9月5日一部改訂、2016年9月3日一部改正)
1.将来、島嶼学および本学会をリードして活躍することが期待される本会の若手会員の顕彰を目的として日本島嶼学会研究奨励賞(以下奨励賞という)を設ける。
2.奨励賞は、授賞年度の4月1日現在45歳以下の本学会の会員で、以下の選考を経て選ばれた者に授ける。
3.奨励賞授賞候補者を選考するため,奨励賞授賞候補者選考委員会(以下選考委員会という)を設ける。
4.選考委員会は、理事会の合議により選ばれた本会の理事若干名で構成する。また、理事会が必要と認めた理事以外の正会員を委員に加えることができる。
5.選考委員の任期は、通常総会の日または理事会が承認した日から翌年の通常総会の日までとするが、再任を妨げない。
6.選考委員会は自薦または他薦により推薦された者の中から授賞候補者を選び、選考理由を付けて理事会に報告する。授賞候補者が無い場合も、その旨を理事会に報告する。選考に際しては、本学会等における既往両3年以内の研究業績(作品・社会活動等も含む)を中心に、将来の可能性も考慮して候補者を選出する。
7.理事会は、選考委員会が選定した候補者について審議し、授賞者を決定する。
8.授賞は原則として毎年若干名とする。
9.表彰は総会において行う。
10.授賞者には賞状および副賞を授与する。
11.この規則の変更には理事会の3分の2以上の同意を要する。
日本島嶼学会研究奨励賞に関する細則
(2013年11月24日制定、2014年9月5日一部改訂)
1.選考委員には、常任理事もしくは副会長の少なくともどちらかと,島嶼研究編集委員長を含む。
2.選考委員の選出にあたっては、学問分野や女性比率に関して配慮する。
3.選考過程において、外部から授賞候補者に関する情報を参考聴取することも可能とする。
4.選考委員長は、選考委員の互選により選出する。
5.賞状および副賞は、選考委員長が準備する。
6.賞状の書式は、選考委員会で 定め理事会に報告する。
7.副賞は、1名につき10000円(現金)とする。
8.授賞理由は学会のホームページで公開する。
9.この細則の変更には理事会の2分の1以上の同意を要する。